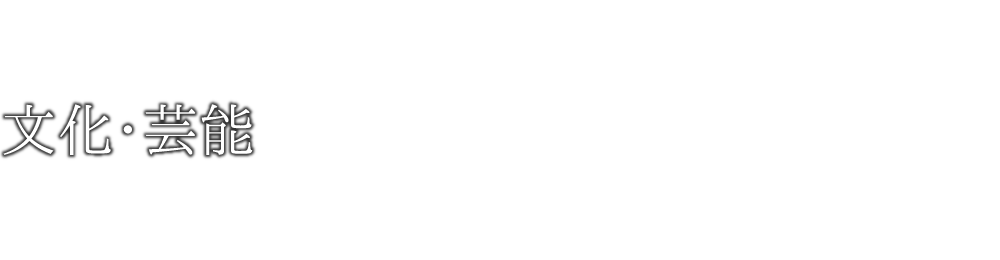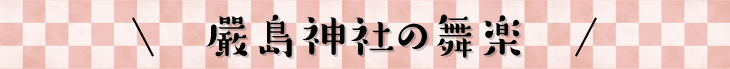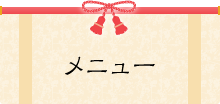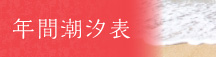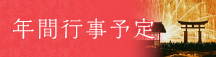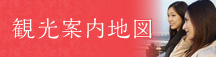嚴島神社の舞楽について

舞楽とは、上古、インド、中国、朝鮮半島を経て日本に伝えられた音楽(雅楽)と舞いのことですが、発祥の地インドはもとよりベトナム、中国、朝鮮半島にも現在は残っていません。
12世紀後期平清盛が大阪四天王寺から楽所を宮島に移して盛んに奉奏されました。蘭陵王[らんりょうおう]・納曽利[なそり]・万歳楽[まんざいらく]・延喜楽[えんぎらく]など二十数曲が現在も嚴島神社に伝承されています。
曲名
| 振鉾 [えんぶ] |
 舞楽の最初に舞われる儀式的な舞曲で、天地の神と祖先の霊に祈りを捧げ舞台を清める宗教的な意味をもっています。
舞楽の最初に舞われる儀式的な舞曲で、天地の神と祖先の霊に祈りを捧げ舞台を清める宗教的な意味をもっています。 |
|---|---|
| 蘭陵王 [らんりょうおう] |
陵王ともいい、約千四百年前、中国の北斉の国王蘭陵王長恭[ちょうきょう]は、周の大軍と金 城下で戦い大勝をして勇名を天下に轟かせました。その武勲を称え作られたと伝えられています。    
|
| 萬歳楽 [まんざいらく] |
 唐の聖王の時代、鳳凰[ほうおう]が飛来して君萬歳[ばんざい]を唱えたので、その声を楽に写し、その姿を舞いに振り付けたという。
唐の聖王の時代、鳳凰[ほうおう]が飛来して君萬歳[ばんざい]を唱えたので、その声を楽に写し、その姿を舞いに振り付けたという。 |
| 延喜楽 [えんぎらく] |
 醍醐天皇の908年に藤原忠房が曲を作り、式部卿敦実親王[しきぶきょうあつざねしんのう]が舞いを作り、年号の延喜を曲名としたと伝えられる。
醍醐天皇の908年に藤原忠房が曲を作り、式部卿敦実親王[しきぶきょうあつざねしんのう]が舞いを作り、年号の延喜を曲名としたと伝えられる。 |
| 納曽利 [なそり] |
 蘭陵王の答舞で、雌雄の龍が昇天する姿を模しているといわれ、一名双龍舞といいます。
蘭陵王の答舞で、雌雄の龍が昇天する姿を模しているといわれ、一名双龍舞といいます。 |
| 太平楽 [たいへいらく] |
 中国漢の高祖[こうそ]が頂羽[ちょうう]の臣頂荘[ちょうそう]が、舞いを装って剣を抜き、高祖を狙ったところ、高祖も舞いながら袖で剣を防いだため果たし得なかったという故事によって作られたという曲で、厳めしい中国の武将の舞いです。
中国漢の高祖[こうそ]が頂羽[ちょうう]の臣頂荘[ちょうそう]が、舞いを装って剣を抜き、高祖を狙ったところ、高祖も舞いながら袖で剣を防いだため果たし得なかったという故事によって作られたという曲で、厳めしい中国の武将の舞いです。 |
| 狛鉾 [こまぼこ] |
 高麗[こうらい]の貢ぎ物を運ぶ船が、五色の彩色をした棹で船を操って港に入る有様を舞いにしたといわれています。
高麗[こうらい]の貢ぎ物を運ぶ船が、五色の彩色をした棹で船を操って港に入る有様を舞いにしたといわれています。 |
| 抜頭 [ばとう] |
 インドの話で、父親が猛獣に殺されたのを息子が知り憤って、仇を討とうと山中に分け入り、めでたく本懐を遂げ、勇躍下山する様を舞いにしたものといわれています。
インドの話で、父親が猛獣に殺されたのを息子が知り憤って、仇を討とうと山中に分け入り、めでたく本懐を遂げ、勇躍下山する様を舞いにしたものといわれています。 |
| 一曲 [いっきょく] |
左方の舞人は鶏婁鼓[けいろうこ]を首から吊り、右手に桴を持ち、左手に振鼓[ふりつづみ]を持って高くかかげ、拍子に合わせて打ち鳴らします。右方の舞人は壱鼓[いっこ]を首から懸紐で吊り、右手に持った桴で曲の各拍子ごとに打ちます。 |
| 蘇利古 [そりこ] |
 応神天皇の御代に、酒を造ることを専門としていた百済からの帰化人須須許理がこの舞いを伝えたという。
応神天皇の御代に、酒を造ることを専門としていた百済からの帰化人須須許理がこの舞いを伝えたという。 |
| 散手 [さんじゅ] |
 釈迦が生まれたときにこの曲が作られたと伝えられる勇壮な武将の舞いです。
釈迦が生まれたときにこの曲が作られたと伝えられる勇壮な武将の舞いです。 |
| 貴徳 [きとく] |
 勃海(シベリア)方面から伝えられた曲で、漢の帝王に降伏して帰徳公と名乗った勇将がおり、その勇姿を模した舞いといわれています。
勃海(シベリア)方面から伝えられた曲で、漢の帝王に降伏して帰徳公と名乗った勇将がおり、その勇姿を模した舞いといわれています。 |
| 胡徳楽 [ことくらく] |
 舞人四人が舞台に上がり、次いで瓶子を取り出して酌をする。勧杯は、冠に雑面をつけ、瓶子取りは二の舞の笑面をつける。舞人が酔って舞う間に、瓶子取りは独酌で酒を飲み、千鳥足で舞台を退出する滑稽な舞いです。
舞人四人が舞台に上がり、次いで瓶子を取り出して酌をする。勧杯は、冠に雑面をつけ、瓶子取りは二の舞の笑面をつける。舞人が酔って舞う間に、瓶子取りは独酌で酒を飲み、千鳥足で舞台を退出する滑稽な舞いです。 |
| 還城楽 [げんじょうらく] |
 唐の玄宗皇帝が韋后の乱を平らげ、夜半宮城に凱旋されたのを祝って作られた曲と伝えられ、西域の人は蛇を好んで食べることから、蛇を見つけて喜ぶ様を舞いにしたといわれています。
唐の玄宗皇帝が韋后の乱を平らげ、夜半宮城に凱旋されたのを祝って作られた曲と伝えられ、西域の人は蛇を好んで食べることから、蛇を見つけて喜ぶ様を舞いにしたといわれています。 |
| 甘州 [かんしゅう] |
 唐の玄宗皇帝が、大后と青城山に行ったとき、官女の衣が風にたなびき、仙女が舞っているように見えたのでこれを舞いにしたといわれる
唐の玄宗皇帝が、大后と青城山に行ったとき、官女の衣が風にたなびき、仙女が舞っているように見えたのでこれを舞いにしたといわれる |
| 林謌 [りんが] |
 唐楽の林謌を高麗楽に写したもので、舞人は特殊な甲を被って舞います。
唐楽の林謌を高麗楽に写したもので、舞人は特殊な甲を被って舞います。 |
| 桃李花 [とうりか] |
桃花祭用の曲で、宮司が桃の花を本殿にお供えする間奉奏(ほうそう)する曲です。 |
| 賀殿 [がでん] |
菊花祭用の曲で、宮司が菊の花を本殿にお供えする間奉奏する曲です。 |
| 長慶子 [ちょうげいし] |
舞楽の退出音声として奏する曲です。 |
年中行事表
| 月日 | 祭典名 | 曲名 |
|---|---|---|
| 1月1日 午前5時から |
歳旦祭 | 振鉾 |
| 1月2日 午前9時から |
二日祭 | 萬歳楽・延喜楽 |
| 1月3日 午前9時から |
元始祭 | 太平楽・狛鉾・胡徳楽・蘭陵王・納曽利・長慶子 |
| 1月5日 午前5時30分から |
地久祭 | 振鉾・甘州・林謌・抜頭・還城楽・長慶子 |
| 2月23日 午前9時から |
天長祭 | 振鉾・萬歳楽・延喜楽・蘭陵王・納曽利・長慶子 |
| 4月15日 午後5時から |
桃花祭 | 振鉾・萬歳楽・延喜楽・桃李花・一曲・蘇利古・散手・貴徳・蘭陵王・納曽利・長慶子 |
| 5月18日 午前9時から |
推古天皇遙拝式 | 振鉾・萬歳楽・延喜楽・蘭陵王・納曽利・長慶子 |
| 旧暦5月5日 午後2時から |
摂社地御前神社祭 | 二曲奉奏 (曲目は決まっていない) |
| 旧暦6月5日 午前9時から |
市立祭 | 振鉾・萬歳楽・延喜楽・蘭陵王・納曽利・長慶子 |
| 10月15日 午後5時から |
菊花祭 | 振鉾・萬歳楽・延喜楽・賀殿・一曲・蘇利古・散手・貴徳・蘭陵王・納曽利・長慶子 |
| 10月23日 午前10時から |
摂社三翁神社祭 | 二曲奉奏 (曲目は決まっていない) |